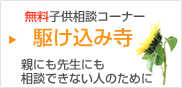エッセイ「曙光(ショコウ)」母を失った娘の思い 第1回 ニューヨーク州ロングアイランド
曙光
藤井 奈緒
母は大きく息を吸い、ポロンと涙を流した。
この時、私の中で時間は止まったように思える。この沈黙の時間の中で私は何を感じていたのだろうか。母は私の犠牲になったという感覚があったように思う。他方では、私が母の犠牲になったという感覚もあったに違いない。しかし、意識が凍り付いてしまったような時間の中で何を感じ何を考えていたのか、私には分からない。
=ニューヨーク州ロングアイランド=
三歳の頃から、私はアメリカに住んでいた。ニューヨーク州の南東部に位置するロングアイランドというのどかな島で幼少期を過ごした。振り返ると、いちばんに自分らしさを感じるのがここでの時間だ。自分という意識の起源はこの場所にあるように感じる。
不思議なのは近所の子達とのコミュニケーションに困った覚えがないということである。生まれは日本なので、最初から英語を話していたということはない。自分らしさを主張することにかけてはことさらに強い面々の中にあって、自分はシャイな子に分類されていたに違いない。それでも、それなりに天真爛漫でいられたのは、体を駆使したジェスチャーだったのか、顔の表情で意思を伝えあっていたのか、今となっては分からない。しかし、私は小遣い稼ぎに路上でレモネードを売っていたりしたのだ。おそらく自意識がなかったからこそ出来ていたことに違いない。
あれは小学校の二年生の時だった。歴史の授業でインディアンについて学んで夢中になった。ネイティブ アメリカンという敬称で呼ばれる彼らの物語は、大人から子供たちへとても肯定的に語り継がれているように思う。ネイティブ アメリカンを英雄的に語る事は、ある意味、アメリカの過去の行いに対する贖罪なのかもしれない。
子ども心にそんなことは知る由もないが、先住民に対するアメリカ人のリスペクトは非常に強いものがあった。自然と共に生きる人々で、彼らの根底にあるものは自分を信じるという強さである。感じるままに語り、思いのままに行動する。仲間を大切に思い、部族の尊厳を守る。自然の中で多くを感じ取り、多くを考えながら日々大地に感謝を捧げ、祈り、生きることが彼らの真実なのであった。
しかし、このような生きる価値を幼い私が理解していたわけもない。それでも、私は木に登ってインディアンの生活に思いを馳せながら、何時間も過ごすような子どもだった。木にはペットの様に名前を付けていたし、草や土に触れるのが好きだった。今でも高原などに行って折れた草から流れ出るほのかな青臭い匂いを嗅ぐと、インディアンの世界が蘇る。
ある時、学校の裏の空き地で赤い土が露出しているところを見つけ、その土を水で溶いてフェイスペイントをしたのも、インディアンへの憧れをはっきり持っていたからだ。私の髪は黒く、日焼けしていたから容姿はそれなりに近いものがあったかもしれないし、インディアンに近い自分の外見を意識したこともはっきり覚えている。
この頃、自分が「イエロー」と呼ばれる人種である事も分かっていた。白人はWhiteで、黒人はBlack、自分はYellowという訳だった。I’m from Japanというのはお決まりの台詞でどこに行っても繰り返していた。日本では、「私は日本人です」と言う機会はほとんどないのだから、この台詞はいくらか私のアイデンティティを強めたに違いない。
(続く)
- カテゴリー: エッセイ「曙光」藤井奈緒 |
- 投稿日: 2018年07月21日 |