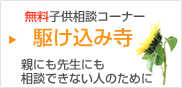エッセイ「曙光(ショコウ)」母を失った娘の思い 第6回「母の死」
=母の死=
最期の一か月、母は鼻に酸素チューブを挿し、話はほとんどできない状態になった。母の体重は半分になってしまっていた。枝のように細くなった腕には点滴が繋がれていた。もう誰にも希望はなかった。「なんとか乗り越えよう」と父は言っていたが、私も父のその嘘に気が付かないようにしていた。
癌は母の肺を侵していた。母はまるで溺れる人のようだった。最期の息を大きく吸い、ポロンと涙を流して母は逝った。母の意識の鮮明さを思う時、神はなぜ母に幸せな死を与えてくれなかったのかと思う。しかし、幸せな死とは一体どういうものなのだろう。母ははっきりと次の一瞬に訪れる死を意識して涙を流した。母の時間はこの時に止まったのだ。これには疑問の余地がない。
=葬儀=
母の葬儀にはたくさんの人が来てくれたが、式が母にふさわしいとは思わなかったし、母の死を参列者と共有できるとも思わなかった。それどころか母の人生に関わった人々が母の死を受け入れ悲しんでいる姿に、湧きあがったのはどうしようもない不快感だった。今思うにあの時の不快感は怒りだったのだと思う。あの人たちにとって母の死はすでに一つの事実でしかなく、なんら不可解なものではない。想像を絶する物語があるのに、彼らにあっては憐れみの陰に隠れて、その物語は全く見えていない。彼らは皆、母の命を終わったものとして心に終おうとしている。なぜ彼らにとって母の死は不可解な事ではないのだろうか。私にとってロイの死は不可解だった。母はロイの半分で人生を終えなければならなかった。あの人たちは、この理不尽さになぜ驚かないのだろう。
彼らにとって「他人の死」がどれだけあっけなく、そしてすんなりと日常に溶け込んでいくものか私は想像した。彼らの生活がすぐに元に戻る事は明らかなように思われた。彼らは私のように罰せられることはない。確かに私は母の死によって罰せられた。なぜ母が死ななければならなかったのか。それは私のせいなのだ。私のせいで母は死ななければならなかった。だから、私は罰を受けたし、その罰が終わるとも思っていない。未来永劫、この罰を受け続けるつもりだった。
(続く)
- カテゴリー: エッセイ「曙光」藤井奈緒 |
- 投稿日: 2018年07月29日 |