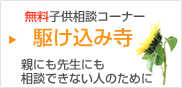エッセイ「曙光(ショコウ)」母を失った娘の思い 第5回「I don’t care.(私、気にしない)」
=I don’t care.(私、気にしない)=
ロイの死によって私が獲得した世界は、どことなくよそよそしくて居心地が悪かったのだが、透明で無機質で明るかった。そこは自分を見つめその自分を正直に語れば受け入れてくれる世界だった。自分が言い放った言葉が自分にとって真実でありさえすれば、その言葉は受け入れられた。時には称賛さえ受けるのだが、もちろん、時には反論されることもあった。だが意見に反論されても、人格を否定されることはなかった。肝心なのは、その結果が称賛であれ、厳しい反論であれ、私がそれから自由で居られたということである。だから、I don’t care.(私、気にしない) というのが私の口癖だった。
=怖れ=
この口癖がけっして通用しない日本の現実を、私が恐怖感をもって見つめていたことに気が付いたのはいつの頃だっただろうか。中学時代、幾度となく疲れ果てて不登校になった。しかし、自分がなぜこんなにも疲れ、満足に学校にさえ行けなくなるのか、その理由がどうしても分からなかった。私は母に何を訴えていたのだろうか。それが分からないのに、私は母が自分を理解しないと言って母を責めた。私は母への依存を深めていった。その依存には当時から罪悪感があって、それ故になのか、私はいつしか母の死を怖れるようになった。自分の事で分かっている事と言えば、私は母の死を怖れているということだけだったと言って良い。
=祈り=
そんな中、知らされたのは母が癌で余命いくばくもないということだった。それは、本当におあつらえ向きに、まるで正確に計ったようにもたらされた。その知らせは、たちまち宇宙になって私を包んだ。すべてが無限に遠ざかって無音の響きに打ちのめされたようだった。これが、この力が運命なのかという思いが浮かんだことを思い出す。その運命が告げていることは、母が居なくなるということだ、ということは分かっていたような気がする。だが、どうしてもその自分の理解を受け入れることが出来なかった。私は祈り始めた。しかし、その祈りが叶えられると信じたことがあったのだろうか。祈りが強ければ強いほど希望は遠ざかって行ったように感じる。
母が苦しむことは私が苦しむことだった。そして、私が苦しむことは母が苦しむことだった。だが、私は母が喜んでいる時でさえ痛みに苛まれた。じっさい、母の喜びを痛みとして感じるほど病状の悪化は早かった。母と私が過ごす世界は外の世界と切り離されていて、私には生きているという感覚はなく、ただただその世界の終わりを待って居る間延びした時間がいつも止まりかけているように感じられた。母は化学療法を受けたが、効果はなかった。
(続く)
- カテゴリー: エッセイ「曙光」藤井奈緒 |
- 投稿日: 2018年07月28日 |