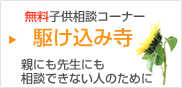エッセイ「曙光(ショコウ)」母を失った娘の思い 第3回 初めての死
=初めての死=
それからどれくらいの月日が経っただろうか。ある日、学校から帰ってくると玄関先で母が大家さんと話しているところだった。母は何度も頷き、しきりにどこかの場所を確認しているようだった。ロイが亡くなったということを聞かされたのはその晩の事だったように思う。どうやら旅先のカナダで倒れたらしいということだった。大家さんの話は、通夜が行われるので近隣の人で見送ろうというお誘いだったのだ。
指示された場所に行ってみると、そこは地域の集会場だった。アメリカではクリスチャンが圧倒的に多いため、教会ではない場所での葬儀はとても珍しいことだったのではないかと思う。集会場のホールで行われたので、とてもこじんまりしていてカジュアルな通夜だった。
アメリカでは宗教に属している事の方が当たり前と言って良いように思う。友達の家に食事に招かれたときに、お祈りの前に「Naoの宗教は?」と聞かれることがよくあった。食卓を囲む者同士が手をつないでお祈りすることもあったので、そう訊ねることはたぶん私に対する敬意だったのだと思う。きっとロイには通っている教会がなかったに違いない。
ホールの入り口には生前彼が旅先で撮ったのだと思われる写真がずらりと飾られていた。入り口を抜けると、室内はぼんやりとしたオレンジ色の照明で満たされており、想像していたよりもずっと明るい雰囲気だった。棺の中を覗いて、初めて、ロイはこんな顔だったのかと私は思った。その時、私は初めてロイの顔をまじまじと見つめたのだった。
庭先で思いがけずロイに会うと、彼は必ずニコッと笑いかけてくれた。その限りなく善良な笑顔に、私はいつも照れ隠しの仏頂面を返したのだった。ロイは仏頂面の陰に隠された私の好意をきっと分かっていたに違いない。私もその事を知っていたのだと思う。そうでなくてどうして仏頂面など出来るだろうか。
彼が亡くなったと母から聞いたとき、私は何を感じていたのだろうか。いま目の前にロイは横たわっていた。ロイが死んだという事実だけがぽつんとそこに横たえられて置き去りにされていた。
この時までの自分は、喜んでいるにせよ、悲しんでいるにせよ、そのどちらでもない平坦な気持ちでいるにせよ、自分の感じるままに感じて自らを省みることなどなかった。だが、この時初めて、自分の感情を自分のものとして感じたのだった。自分の感情を意識に捉えたこの時以来、何かがずっと続いて来て、今、現在進行形としての自分の意識に繋がっていることに私は気が付いている。というより、それに気が付いた私が今も継続して私を見つめていると言いたい。
だからと言って、あの時感じたものが哀しみであったとか喪失感であったとか言うとすれば、それはまったく当たらない。私はその時ちっとも悲しんではいなかった。
私にとって初めての死がロイだった。人の死を受け入れるも受け入れないもないのだろうが、全く不可解なものが私の心を捕らえていた。この不可解さを今考える時、色々な思いが心を駆け抜けていく。その不可解さは、彼が終始独りだったことに関係しているのかもしれないと思う。あのお通夜の時にロイの家族は一人も来ていなかったように思う。大人になったら当たり前のように誰かと結婚し子供を設け同じ家で暮らすのが普通の事だと思っていた。それなのにロイはあの大きな家に一人で住み、一人で旅に出て、一人で死んで帰って来た。幼い私にとって、人が一人で死んでいく事が不可解だったのかもしれない。
悲しみは遅れてやって来た。ロイが死んでもう一週間以上たった頃だったと思う。ロイの住んでいた隣家には大家さんが移り住んでくるという話を母から聞いていた。学校から帰ってきた時、入りかけた戸口から振り返ってロイの家を見た時に、どうしてか涙が込み上げてきた。母は何も聞かずに膝を折って私の背中をさすってくれた。母は私が何を思って泣いているのかすぐに分かったのだ。
(続く)
- カテゴリー: エッセイ「曙光」藤井奈緒 |
- 投稿日: 2018年07月24日 |